ストーリー

日々、暮らしにくくなっている昨今、何によりどころを求めればよいのか。何もしなければ時間だけが過ぎてゆく。かといって、自分にノルマを与えすぎるとメンタルに来てしまう。そんな時の箸休めに「寝る前の5分間で読むチョイ恐ミステリー」でものぞいてみて。
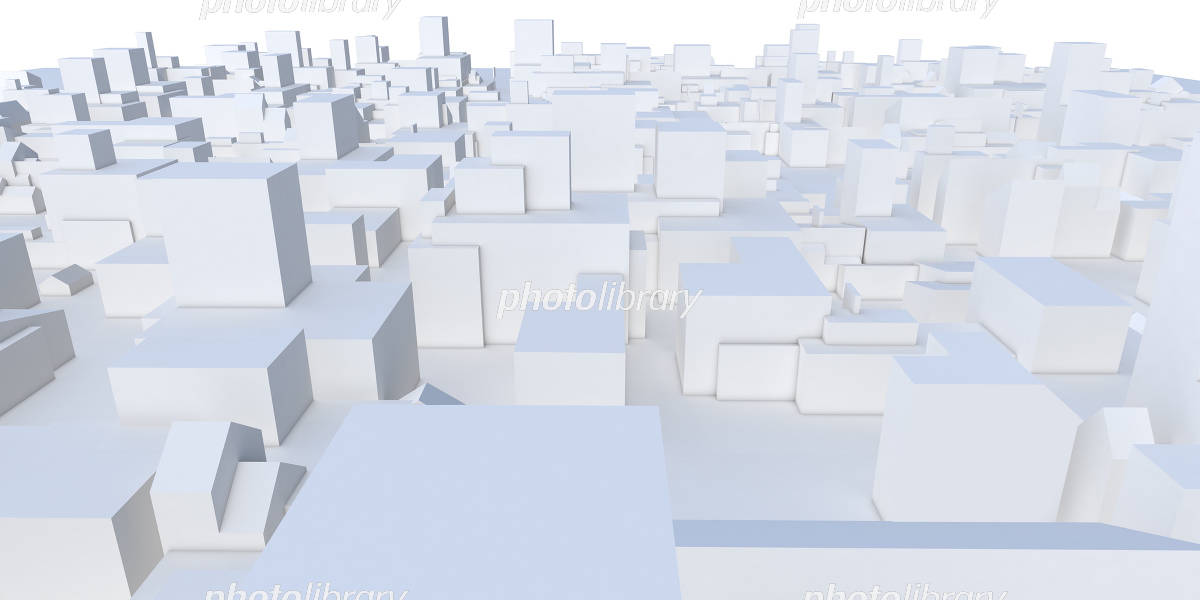
昨日、不思議な夢を見た。周りが全て「白色」の世界だ。雪が積もった銀世界ではない。画用紙のような白色が続く世界だ。白い家、白いビル、白い道路、白い電柱・・・空も厚い雲に覆われている。そして、この白い世界を僕が一人歩いてゆく。
この白い世界は無機質だ。人々が住んでいる気配がない。砂漠のような不毛地帯をさまよってゆく・・・何を求めて。白い家々には窓やドアや灯りもない、僕を完全に拒絶している。
それでも僕は歩き続ける。しばらく行くと、ふと斜め前方が目に入る。丘の中腹あたりにポツンと1軒の赤い家がたたずんでいた。僕はそこに急いで向かった。赤い家にはドアがあった。ドアを開けてみると中に若い女性がいた。見覚えのある顔だ。

女性は僕を見ると微笑み、後について来いと家の奥へ進む。奥には真っ黒なトンネルがあり、しばらく進むと明かりが見え始めた。そして光まばゆい世界に出る。
その世界は見渡す限りの草原だ。雲一つない、真っ青な空と永遠に続く草原。ところどころに芝生が絨毯のように敷き詰められている。そこには多くの人々が寝そべったり、話をしたり、弁当を食べたりとのんびり過ごしている。
草原を走り回る子供たち、ボール遊びをしている人々・・・心地いい風が吹き抜ける。まるで天国のような場所だ。こんなところに一生住めたらいいなと心底思う。草原にはところどころに木々が茂っている。

この世界は実在するのか。僕は木の葉っぱを一枚取って観察した。その時少女が近寄ってくる。彼女は「ここにいる全員が葉っぱを一枚づつ取ったら木が枯れてしまう・・・それでいいですか」と優等生ぶる。「ごめんなさいね」と急いで退散する。純粋な子供には付き合いきれない。
周りの人々をよく見ると、見覚えのある人がちらほら見える。しかも、その人たちはだいぶ前に亡くなっている。そうするとここは天国と言う楽園なのか? 僕を連れてきてくれた少女をマジマジと見る。思い出した。近所に住んでいた幼なじみだ。でも彼女はかなり前に病気で亡くなっている。
ふと右を見てみると白い犬が近寄ってくる。「太郎だ」亡くなってしまったが僕が昔、可愛がっていた柴犬だ。太郎はこちらに来いと僕を森の中に誘う。後について森を駆ける。太郎はスピードを上げるからなかなか追いつかない。

森の外に出たところ、突然そこはガケになっていて、僕は暗い奈落に落ちてゆく。現実の僕は足をバタバタさせて目が覚める。夢だったんだ。寝汗をだいぶかいていた。
白い色は僕の好きな色の一つだ。白は清々しさ、清潔さ、若々しさ・・・を強調する。「白い色は恋人の色」なんて歌が大昔に流行った。白は誰からも好かれる色なんだ。
ところが、僕には過去、うっとうしく思われた時期があった。病院の白い壁、入院していた病室の白いカーテン、白いシーツ、そして主治医の白衣・・・。毎日「白」に囲まれて過ごす、時々それが血に染まる。何かが僕を襲ってくる恐怖が心臓を締め付ける。

長い闘病生活、この白い世界から解放される日は来るのかと悩んだ時期もあった。それが心の奥底にトラウマとなって潜んでいた。この潜在意識が夢となって現れたのかもしれない。
この白い世界から救ってくれた少女は近所に住む幼なじみだ。彼女は全く変わらない若いまま。でも僕は老人になってしまった。そしてあの世から現世に引き戻してくれた「太郎」。よく一緒に散歩した、野原も駆け巡った。その「太郎」も突然亡くなってしまった・・・ショックだった。
僕の周りの人々は僕を残してみんな逝ってしまう。僕は2度ほど死にかけた。だから「死への恐怖」は和らいでいると思っていた。でも時としてこのような夢を見ることを考えると「死への恐怖」は和らぐどころか強くなっている。

見渡す限りの草原「天国」と思われる場所。そこには、後で考えてみると死んだ人ばかりではない。現在生きていて僕とも顔見知りの人がいた。
その人は最近、救急車で運ばれたことを知っている。幸い、命に別状なかった。しかし、そのことが心に引っかかっている。これは予知夢なのか、いや違うのか。人間誰でもいつかは死ぬ。僕自身もお迎えが来る日がだんだん近づいている。
予知夢でないことを祈っている。
TATSUTATSU
























この記事へのコメントはありません。